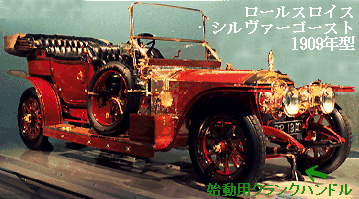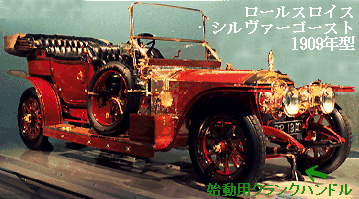|
「ロンドンの叔母さんのお手製ですよ」
説明する思音に軽く会釈をして、メイドが銀の菓子器に盛ったかりん糖を摩利の前に置く。
「わあ、なつかしいなぁ」
自分の気を引き立てるように摩利は声をあげて喜んだ。
「『摩利くんのお土産に』と、叔母さんは私が帰国する前日に届けてくれましたよ。
おいしいうちにいただきましょう」
思音のロンドンのオフィスに姿を見せたロンドンの叔母さん、つまり思音の妹は、「この霧でしょう?
なんでもかんでもが湿気やすくて困ってしまいます」とこぼした。
かりん糖を詰めた茶筒缶は胴と蓋の継ぎ目に目張りまでしてあった。
「今朝、揚げたものですけど、油が回らないうちに食べてくださいね」という妹の言葉を思い出して、思音も故国をしのばせる素朴な菓子をつまむ。
しきりと銀の菓子器に手を伸ばしながら、摩利はどこか上の空だ。
―― 新吾くんが送ってくれた試験問題が気がかりなのだろうか。
今、摩利が持堂院に合格する確信を持てないのは無理からぬことだと思音は思う。
日本語の授業の約束をいつも反故(ほご)にする“家庭教師”は他ならぬ自分だ。
「持堂院の受験に備えて、そろそろ日本から家庭教師を呼びましょうか」
黒砂糖をまぶしたかりん糖の甘さが広がる口から、ほろ苦い自責を含む言葉が出る。
「今から急いで手配してもこちらに到着するのは二月(ふたつき)は先になるでしょう。
それじゃあ、せっかく日本から来てもパリで教えてもらうのはほんの数ヶ月になってしまいます」
「パリに留学している日本人の中から探すという方法もありますよ。それなら、さほど時間はかかりません」
「……」
「ただ、摩利くんが持堂院に進むことを望まないなら、私はそれでも良いと思っています。
そう、メーリンクのおばあさまが摩利くんをベルリンに迎えたいと言っていることは、この前、話しましたね。
それも一つの道です。
叔母さんの居るロンドンに留学しても良いし、むろんパリで私と暮らしながらこちらの学校に進学するのも良いでしょう。
きみが望むのであればどれでも正しい道だと思いますよ」
―― 持堂院、ベルリン…、進路を決めなければならないのはおれも同じなのか。
いや、アグネスもウルリーケもベルリンに6月には帰ると断言している。
そうすると、決まっていないのはおれだけか…。
かりん糖はさくさく音を立てて口の中で崩れる。
その歯切れよさとは裏腹に、自分の答えが煮え切らないのが歯がゆい。
―― だからと言って、忙しいとうさまに心配をかけたくない。
4日前の記憶がふと頭をもたげ、自分自身への欺瞞をあざわらう。
―― おれの中に、とうさまに話せないこと、話したくないことが増えているだけだ。
「ええ、とうさま。おれも、もう、決めなければならない時期だと思います」
明るく返事をしてみても、そのぎこちなさは明白だった。しかし、思音は笑顔でうなずく。
―― 息子を信用しているといえば聞こえはいいが放任と紙一重、親としては無責任だとボーフォール公には非難されそうだ。
|